
12月読書会
『赤毛のアン』
L・M・モンゴメリ著 松本侑子訳 文春文庫 2019年7月発行
12月18日14:00~16:00 千代田区立図書館 参加者8名
プリンス・エドワード島のアヴォンリー村で、初老の兄マシューと妹マリラが暮らしていた。独身で子どものいない二人は、農場の手伝いをする男の子を孤児院に頼む。だが、グリーン・ゲイブルズにやって来たのは赤毛でやせっぽちの11歳の女の子アン・シャーリーだった。アンは生後3か月で両親を失い、引きとられた先では家事と子守りに追われ学校にも行かせてもらえない生活を送ってきていた。アンにどこか惹かれ、手伝いとしてではなく家族の一員として引き取ることに決め、三人の暮らしが始まる。アン16歳までの物語。
テーマは、①人に対する尽くし方②日常を豊かに生きていく想像力③未来を信じ一直線に努力していく前向きさ。マシューの「わしらがあの子の訳にたつかもしれないよ」や、進学を諦めるしかないアンの「曲がった先には最高のものが待っている、そう信じることにしよう」という言葉や印象的な場面も数多く挙げられました。そして、日本の現状として乳児院や児童養護施設にいる子どもたちの9割に実の親がいること、養子縁組制度の難しさにも話が及びました。
作者モンゴメリがプリンス・エドワード島で育ち、幼い頃から物語を書いていたことや教員免許を取得したことなどが作品に投影されていること。また、モンゴメリは児童向けの物語を書くことは好きだが道徳を入れないと本が売れないと言われ、編集者によって道徳の注入具合を変えていたというエピソードの紹介がありました。O さんが作家について調べた本『険しい道:モンゴメリ自叙伝』は、グリーン・ゲーブルズにも行ったほどアンのファンであるお姉さんの愛読書だそう。繰り返し読まれ背表紙が外れバラバラになったその本からも、紀行、料理、手芸、写真集・・など、たくさんの関連本が出版されているアン・シリーズの魅力を再認識させられました。
かつて村岡花子訳で出会い、今回完訳版を再読した参加者たち。完訳版だからこそ味わえる描写の豊かさに満たされました。が、現地で取材することができなかった時代に、村岡花子が英語力・表現力を駆使して外国文学を持ち込んでくれたことに敬意を表したいとの声も上がりました。『赤毛のアン』は、読むたびに違う感動を与えてくれる名作であり、世代や性別を越えて楽しめる本であることを共感しながら読書会を終えました。(記録:平島和子)

11月読書会 日時:11月29日 参加者9名
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』
ブレイディみかこ著 発行:2019年6月20日 新潮社
著者は福岡の進学校を卒業後アルバイトをしては幾度も渡英し、英国で保育士の資格を取り、働きながらライター活動を始めた。今、書店には彼女の著書が平積みされるほどの書き手である。配偶者はアイルランド出身の元銀行員で今は大型ダンプの運転手。一人息子と3人でイングランドの地方都市に住んでいる。息子は著者が「底辺託児所」と勝手に呼んでいる保育施設(著者自身もここで見習いとして働いていた)ですくすくと育ち、カトリックの名門小学校に進学。しかし、中学はなんとなく見学に行った近所の「元底辺校」に入学する。「元」というのは、校長や教員が演劇や音楽などの中で生徒がやりたいことをのびのびとやらせる方法を積み重ねていき素行や学力もよくなってきたからである。とはいえ、様々なことは起こる。移民の子が別の移民の子を差別する。いじめもある。ずっとお腹をすかせている子もいる。そんな息子や友人たちの中学校生活の最初の1年半が書かれている。
今回の話し合いでは、まず主人公である息子の評判が高かった。心根が良い、親に従いつつも自立している等々。それは、一見突き放しているようで子どもと対等に、外に出た時に力になるような話をする両親の子どもへの接し方に育まれているのではないかなど離された。英国では学校教育にシティズンシップ・エデュケーションが導入されている。試験に出された「エンパシー(共感する力)とは何か」という問いに、息子は「自分で誰かの靴を履いてみること(英語の定型表現で、他人の立場に立ってみるの意)」と答える。日本の徳目を押し付けるような教育との違いにも話が及んだ。この本は、多様性のややこしさの中で、しっかり自分の立ち位置を考えながら育つ息子と、共に成長する母親の姿が、爽やかな書きぶりの中に迫力をもって伝わってくる読み応えのあるものだった。(記録:大谷清美)
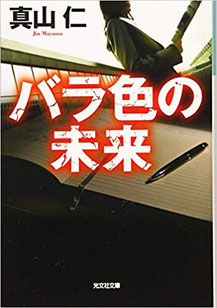
10月読書会 日時:10月23日14時~17時
『バラ色の未来』真山仁著 光文社 参加者:10名
作者の真山仁は1962年生まれ。新聞記者・フリーライターを経て、2004年『ハゲタカ』でデビュー。この本は、NHKドラマとしても放映され大反響を呼んだ。『バラ色の未来』は、1917年に出版された。カジノを含む統合型リゾート(IR以下IRと記す)を描いた社会派ミステリーである。話は、日本初のIRの誘致を目指していた青森県円山町町長鈴木一郎の息子の家が炎上し、嫁と孫が死亡したところから始まる。6年後、鈴木一郎も東京でホームレスとなり死亡する。それらの真相を究明し、IRの問題を提起しようとする東西新聞の記者たちの奮闘を描いている。また、並行してそれらをもみ消そうとする東京進出を目指すシンガポールIRのオーナーの下で働く、日本の広告代理店社員の暗闘も描いている。
結局、日本初のIRは総理のお膝元である山口県関門市に誘致されたが、うまくいかず地元でカジノに興じた多くの人が依存症に悩み、ついには自殺者まででてしまう。また、誘致に破れた円山町の予定地は、廃墟と化していた。
テーマは、IRというバラ色の未来の幻想に踊らされ、欲望に沈み、不幸になる現実であり、その裏には、私利私欲で富を得る権力者や外国資本がある。つまり、IRへの異議申立書である。また、様々な困難を乗り越えて、真実を報道してほしいという新聞記者へのエールでもある。
横浜市民の参加者から、市民の97%がIR誘致に反対している中、議会を通ってしまったと報告があった。この他にもモリカケ問題、利権をあらわにした関西電力の原発問題等々、多くの課題について話し合った。しかし、今の一番の課題は、国民に知らされず、十分に話し合われずに、権力者によって、いろいろなことがどんどん進められてしまうことである。今の日本の現実を見ると暗澹たる思いになるが、真実を見つめ小さなバラの咲く未来を築いていこうという言葉で、読書会を締めくくった。(記録:栗原圭子)

9月読書会 日時:9月27日14:00~16:00
『ハックルベリー・フィンの冒けん』
マーク・トウェイン著 柴田元幸訳
2017年発行 研究社 参加者:10 名
「『トム・ソーヤーの冒けん』てゆう本をよんでない人はおれのこと知らないわけだけど、」と本書は始まる。素直で賢い子だが、きちんとした教育を受けていないハックの語りの原文が、平仮名だらけ間違いだらけの日本語の口語文に見事に翻訳されている。トウェンは『トム・ソーヤの冒険』『乞食と王子』などの作品があり、現代のアメリカ文学に大きな影響を与えた作家である。同時代の日本では夏目漱石の『坊ちゃん』が日本文学を変革する作品として登場。共通したものがあるのではないか。
主人公はハック。自由な暮らしを求め、逃亡してきた黒人奴隷ジムと共に、ミシシッピー川を下り様々な出来事に出会う冒険物語。この物語は、自由とは何かが確立されていない時代の、奴隷にとっての自由や子どもにとっての自由を描いた。冒険は規制の反対側にある。冒険の楽しさや出会いの面白さが子どもたちの共感を呼ぶのではないだろうか。登場人物である大人たちは、ひどい悪戯をも許せる包容力がある。
「大きな川を下るような冒険は今の日本になくなっている」「わんぱく時代の喪失、抹殺と言われ、はみ出す喜びが押しつぶされている」「ハックに憧れてほしいと思う」など、今日の日本の危機的な状況と絡んだ論議も活発に行われた。 「『ハックルベリー・フィンの冒険』をめぐる冒けん」(研究社)柴田元幸の本がこの10月に刊行された。興味深い。(石井啓子)

7月銀読書会『小さな家のローラ』
日時:7月30日13:00~17:00
テキスト:安野光雅・絵&監訳『小さな家のローラ』(朝日出版社)参加者:12名
7月の読書会は、徳島アニマシオンクラブから廣澤貴理子さんを迎えて楽しい時間を過ごした。テキストは、安野光雅さんが今日の子どもたちのために、語り直した『小さな家のローラ』だ。ローラ・インガルス・ワイルダーの『大きな森の小さな家』で広く読まれてきた。今回はあえてこれを語り直した安野さんの本を読み直すことで、その意図をつかもうとした。150年前、つまり日本では明治維新の頃である。深い森の一部を開拓して自然と闘い、自然と共に生きる一家の冬から冬への物語が、ある意味淡々と綴られている。とんでもないハプニングは起きない。父は仕事に一日を過ごし、母は家事と冬のための食糧の保存、衣服の繕いで過ごす。「冬に備えることで春、夏、秋を過ごす」といっていい。鹿や熊の肉を待ち望み、四季折々の節目の行事に親せきや友人、知人ファミリーが集まって歌い、踊ることが唯一の楽しみとする。
— お父さんはお母さんのほうをむいて、いいました。
「お母さんがいれば、だれも飢え死にしないよ、キャロライン」
「まあ、そうじゃないのよ。チャールズ、あなたがわたしたちに食べ物を持ってきてくれるからでしょう」と、お母さんはいいました。
お父さんは満足そうでした。気持ちのいい夜でした。―
この表現に集約されているのではないだろうか。お父さんが弾くバイオリンとその歌が物語を豊かにしている。
議論はあふれるほどに配置された安野さんの挿し絵についてだった。こんなに必要ないではないか、物語は文章で深められるので、わずらわしくしているという意見が出された。しかし、すでに150年を経て、この文章の描いている自然や暮らしをイメージできるだろうか。読者となる子ども・若者はまったく異なるイメージを描いたり、あるいはそれがめんどうで本を手放したりしてしまうのではないだろうか。 安野さんが最近、『足長おじさん』他、児童文学の名作に絵を丁寧に添えた「絵の本」を出しているのは、今日の新しい読者を誘う努力なのではないだろうか。 読書会は、児童文学名作の新訳に挑むことにして、次回は柴田元幸訳『ハックルベリーフィンのぼうけん』をテキストとする。議論を終えて、廣澤さんから徳島でのアニマシオンを掲げた活動の様子を、動画などを含めいっぱい聞いて交流を深めた。まさに、アニマシオンの「たのしいひととき」だった。
朋あり、遠方より来る。また楽しからずや (記録:岩辺)

6月読書会 ヤングケアラ―の葛藤を描く=『レモンの図書室』
6月26日(水)、千代田図書館研修室。今回はいつも半数程度の参加だったが、笠井さんが新しく参加してくれた。『アニマシオンで道徳』の本が届いたところだったので、わっとわいた。困難を抱える大人(親)の世話をする子どもたちの存在が注目されるようになってきた。イギリスではそのためのプログラムも組まれるようになって、いくつもの事例が明らかになってきた。「ヤングケアラ―」と呼ばれる少年少女たち。日本でも、『子ども白書2019』(かもがわ出版)がこのタイトルを目次で掲げていた。中公新書でズバリ、このタイトルで警鐘の書も出ていた。この問題を具体的な姿で示したのが、『レモンの図書室』だ。10才の少女カリプソ。5年前、母ががんのために亡くなって、腕のいい校正作業者である父は悲しみの淵に入りこみ、次第に自制を失っていく。父はレモンに関する著作を書こうとして母の残した膨大な書物を捨て、その棚にレモンを並べる。その著作も出版社から断られると、さらに気力を失くしてしまう。「レモンの図書室」と化すのだ。
カリプソは二人だけの暮らしに押しつぶされそうになりながら、必死に父を支える。母の残した本をひたすらに読むことが、母との会話である。転校生メイは読書好きの少女で,カリプソの親友となる。カリプソの事情を知ったメイの家族ぐるみの支援によってカリプソと父は次第に元気を取り戻していく。
カリプソとメイをつなぐのは二人の大好きな本の話であり、さらに物語を作るという協同作業だ。そして、カリプソは、母と父の物語を書き始める。それを読んだ父は、その物語に参加することによって、自分にとって今、何が大事なことか=つまりカリプソとの生活=を認識してノーマルな意識をとり戻していく。読書すること、物語ることが大きな力となる。
「しんと静まりかえっている。この部屋はわたしのやすらぎの場。目に見えないたくさんの物語に囲まれてすわり、そのなかで息をすったりはいたりする。本のページのなかにとじこめられているキャラクターたちは、だれかが文字を読んでいくだけで自由になれる。本はさまざまなところへ自分を連れていってくれ、現実の生活では決して会えない人々と会わせてくれる。・・・ママがここにいる。わたしはまだママをわすれていない。これからもずっとわすれない。」 父は、「心を強く持っていれば、一人でもやっていけるのだ」と、カリプソに言ってきたが、それは自分自身に言いきかせていたのだった。物語をつくることによってカリプソは気づいていく。「パパはわたしを守るために、おまえがいなくてもだいじょうぶだといいつづけてきた。自分にみたいに傷つかないですむよう、わたし自身の心のまわりに、かべをはりめぐらすようしむけたんだ。 そんなのは大まちがいだ。人には人が必要なんだ。ずっと人を避け続ければ、傷つかないなんて、ありえない。そんなことをしたら、傷ついた上に、さらにひとりぼっちになってしまう。・・・ パパはひとりぼっちじゃない。わたしがいる。つよいこころがどこにあるのか、いまではもうわかっていた。それはほかの人から与えられるもの。だれかがわたしのことを気にかけてくれるということは、その人が自分の一部をわたしに分けてくれているということ。それが力になる・・。」
「わたしはパパのそばにいよう」と、カリプソは心に決める。「人には人の支えが必要だ」とカリプソが理解していくプロセスがていねいに語られている。そう、カリプソの閉じた心の扉をノックしたのはメイだった。 ジョー・コットリル作、杉田七重訳『レモンの図書室』(小学館2018.1)
毎月重ねてもう80冊になる。次は9月30日(金)、『小さな家のローラ』。これは安野光雅さんの訳&挿絵で。
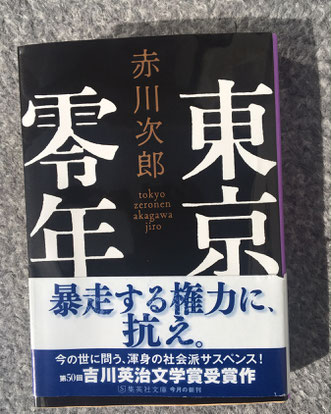
1月読書会『東京零年』
「東京零年」(赤川次郎作)
1月25日 『ファンタジスタ! 92号』発送作業後、開始。
主人公の生田目健司の父は最高検察庁のトップ。いわば権力の中枢に位置する人物である。そんな健司は、水沢亜紀に電車のホームから転落した際に助けられる。それをきっかけに2人は付き合うようになる。水沢亜紀の父水沢浩介は、左派ジャーナリストだったが大規模な反戦集会を企画したところを押さえられ、政治権力に従い、統制下で活動することを条件に政府機関の審議委員などになり、厚遇の扱いを受け、今では脳梗塞で倒れ施設で暮らしている。そのとき一緒に活動した仲間は廃人にさせられたり、処分されたりしている。そんな2人の周りで、権力に従わせようと暗躍する警察、それから逃げようとする人びとが描かれた社会派サスペンスの作品である。
今日の、この作品の世界と日本の社会状況との共通するものについて、話し合いが進んだ。携帯電話のGPS機能があり、監視カメラが至る所につけられ、日常生活は監視下のもとに置かれている。いわば警察国家として政治権力に逆らう者を見つけ出し抹殺しようとする体制が整ってきているといえる。テレビや新聞など報道も権力の都合の良いようにコントロールされ、時の権力の都合にいいニュースが大々的に伝えられている。
作者赤川次郎は、「物事に真髄を見よ、ニュースの裏側に気付け、情報は自分で正しいかどうか見極めよ、とこれからの社会で生き抜く上で大切なメッセージ」(集英社文庫、解説622ページ)をこの作品にこめていることを共感しあった。
『東京零年』という題名についても議論があり、「東京」としたのは、権力の中枢が東京にあることから東京としたのではないか。また「零年」としたのは、健司と亜紀の子どもが生まれることでお話が終わることから、新しい時代への期待をこめて零年としたのではないかという意見が出された。
さらに、この作品で作者赤川次郎は、この監視社会に対する戦い方を提起している。民衆の見えるところで戦うことが大切であり、人々の前に事実をさらすこと、光の中で戦うことが大切だというメッセージを発しているのではないか、という意見も出された。
読書会のあと、2019年1月28日、沖縄辺野古の基地移設反対派のリストが国によって作られていたことがニュースになった。『東京零年』の描いている世界がすぐそこにやってきていることを感じさせる。(記録:渡部康夫)

11月読書会『朝が来る』
著・辻村深月、文藝春秋
11月28日 千代田区図書館
主人公は二人。栗原佐都子夫婦は子どもがほしくて不妊治療を繰り返していたがしていたが効果なく、特別養子縁組で男児を得る。朝斗と名付け、大事に育てる。
その生みの親は、出産時、中学生であった片倉ひかり。両親は教師だが、優秀な姉に比べ、期待された私立中学にも落ちる。家庭での居場所失って、ひかりは巧と関係を結ぶようになり、妊娠、出産となる。子どもはNPOベビーバトンを通じて、養子に出す。ひかりはさらに居場所を失い、家を出て働くが、うまくいかない。さらに働き先での関係から暴力団関係に追われるようになる。追い詰められたひかりは、約束を破り、朝斗の親となっている栗原家をゆすろうとする・・・。
私たちの読書会は、司会、記録、あらすじ、主人公、テーマ、印象的な場面、今日の状況に照らして、という分担でレポートし合い、それを巡って話し合う手法で進めている。
テーマは、「家族のつくり方、あり方」と提起され、共有された。
前半は、養い親の佐都子を主人公とする子育てを巡る問題、後半は産みの親ひかりを主人公とする、10代出産とそれを巡る問題が描かれていく。朝斗が視点となって語る場面も挿入されている。後半は読むのがつらかったという感想が多かった。
しかし、今日、さらに厳しい現実が10代や若い親世代を覆っている。若者の現状も出された。話題は性教育の必要性にまで及んだ。フィクションではあるけれども、切実感のある物語として読まれてほしいと思う。
銀読書会は、6年余、今月で第73回になった。来月は忘年会。時々は一泊旅行や日帰りツアーにも出かける仲良しだ。アニマシオンクラブの中軸メンバーである(コホン!)。(記録・岩辺)

6月の読書会 6月25日(月)
千代田区立図書館 10名『風は西から』 村山 由佳(著) 幻冬舎
この小説の主人公の伊藤千明は、大手の食品メーカーに勤め、コミュニケーション力にも優れ、職場での人間関係にも恵まれ、芯のある女性である。一方、その恋人である健介は、外食産業の会社に勤め、営業部や広告部を経て、それなりの売り上げを誇る居酒屋チェーンの店舗の見習い店長として配属された。将来、郷里の店を継ぐための勉強だと思っていた健介は、短期間のうちにひととおりの業務を経験するシステムはありがたいと思っていた。そこで、店長として店の利益のために一生懸命に働き、将来は千明との結婚を考えていたのだった。だが、従業員からも慕われ、頑張っていた健介が過労自死をしてしまったのである。健介の死を受け入れられずに千明は自分を責め苦しんだが、健介の死の真相を突き止めなければいけないと思い、彼の両親とともに会社との闘いが始まった。
裁判には、健介の同僚、従業員たちも協力してくれた。自死から3年9ヶ月。会社側が千明達の要求をほぼ全面的に受け入れるというかたちで裁判は終わった。
以上がおおまかな内容ですが、つぎのような意見が出された。
♦この本は、社会に理不尽なことがおきたときには、それをはねのけていこうとする姿勢が大切であると伝えている。
♦本の前半では、何とも言えない息苦しさを感じたが、後半では、一気に引き込まれた。♦若い人たちにも勧めたい本である。
また、辛い状況にいる健介へ千明が『あなたなら大丈夫』ということばを投げかけたことで、健介を苦しめたのではないかと悔いている部分があったが、この言葉の重みということを話し合いました。その後、日本の労働状況、特に教員の労働状況、外国での労働に対する考え方、日本での労働闘争、ブラック企業の存在などについて話は広がりました。
この小説の後半の部分は、村山由佳さんが特に練りに練って書かれた部分で、千明の生き方が素直に読み取れる作品だったということで終わりました。現在、この作品は図書館での順番待ちの人が多いという報告がありました。最後に働き方に関する本の紹介もありました。『生きる職場 小さなエビ工場の人を縛らない働き方』 武藤北斗(著)イースト・プレス社 記録 (小山)

5月読書会5月24日(木)午後1時半~4時
於:千代田区立中央図書館 参加者:11名
テキスト:『さよなら、田中さん』
鈴木るりか・作 小学館
「12歳の文学賞」を3年連続で受賞という、鈴木るりかさんのデビュー作がテキストである。
田中花実は6年生。母と二人暮らし。全5編のうち4編はこの花実親子の日常の出来事が綴られている。そこで明らかになるのは、2人の貧しさ、明るさ、生き方の見事さである。そして第5編。花実の同級生、信也が一転して主人公となる。信也は、エリート家庭のただ1人の落ちこぼれで、受験に失敗し、それを恥じる母に山梨の全寮制の学校に入学させられる。
同級生というだけなのに、その確固とした生き方で信也の心に火を灯す花実。もし死にたいぐらい悲しいことがあったら、とりあえずメシを食え、という母も、信也の死への思いを察して彼を支える。
「最初からお父さんがいないから寂しさはわからない。」「生まれ変わっても、私はお母さんと親子ならいいと思う。」花実の単純だがまっすぐな言葉が胸を打つ。裕福な信也の家庭と(母以外、父も姉も兄も、信也を支えようとしてはいるのだが)、激安スーパーを頻繁に利用し、何とか飢えないだけの生活を送っている花実親子の幸福度は比べるべくもない。スーパーのオーナー、大家さんやその息子などの脇役も良い。
何かと話題の作者だが、この本を手にとって、その描く世界の真っ当さ、人情あふれる世界に感心した。 巧みなセリフや構成、語彙の豊富さなども並ではない。作者の父親は「寅さん」ファンだとか。今後のるりかさんの活躍に期待したい・・・ということで読書会一同、意見が一致した。(記録:千田)
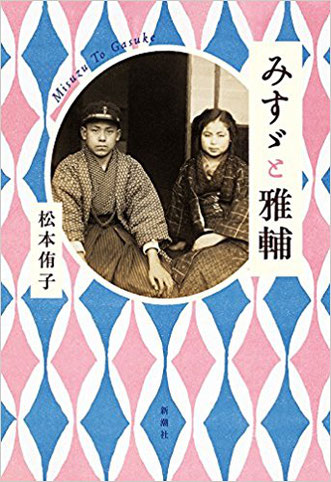
1月読書会1月25日(木)
テキスト(『みすゞと雅輔』松本侑子著 2017.4 新潮社)
この本は、2014年に発見された金子みすゞ(本名=テル)の実弟である上山雅輔(がすけ。本名=正祐・まさすけ)の日記等の膨大な資料をもとに、金子みすゞと上山正祐の交流を描いた小説である。
テーマは、金子みすゞにとって詩とは何であったか、金子みすゞを死に追いやったのは何であったか、ということであろうと考えた。
正祐はみすゞ(テル)の実弟であるが、幼くして母の妹(テルにとっては叔母)の嫁ぎ先である下関の上山家に養子に出される。叔母の死後、正祐の養父とテルの母が再婚したため、テルも下関の正祐の家に移り住むことになる。テルと正祐は実の姉弟でありながら、義理の姉弟となる。正祐は、音楽学校に進学する夢を捨て、家業の書店を継ぐために東京の大きな書店に丁稚奉公に行くことになるが、関東大震災により仕事がなくなり下関に帰ることになる。一方、テルは、店の番頭である宮田敬一と結婚することになる。思うようにならないジレンマの中で正祐は、花街に出かけて放蕩生活を送るようになる。そんな正祐に対して、お金持ちの坊ちゃんのわがままな生活態度に疑問を感じるという意見も出された。
テルは、金子みすゞというペンネームで、幼年雑誌や児童文芸誌などに多くの詩や童謡を投稿し、西條八十など当時の詩壇をリードする作家達から高い評価を得ていた。しかし、詩や童謡を投稿していた雑誌が廃刊となり、時代は大正デモクラシーから昭和のファシズムへと大きく変遷していく。そんな中、テルは、敬一と離婚し、自ら死を選ぶこととなる。どうして、テルは死を選んだのか、その理由について意見を出し合った。女性の権利やキャリアが認められない社会への抗議ではないか、童謡を発表する場がなくなり、童謡詩人としての行き先に不安を感じたからではないのか、大正の童心主義の終焉を感じ取ったのではないか、自死をする前に撮った写真には、並々ならぬテルの決意が感じられる、将来、詩集が出版される際に、巻頭を飾るために撮ったのではという作者の考察に共感する、などの意見が出された。また、正祐は、良心の呵責に苛まれたと書いてあるが、本当にそう思ったのか、疑問であるという意見も出された。
今日の時代状況は、大正デモクラシーからファシズムへの流れるこの時代と似ていて、再び戦争へと向かう気配も見られる。作者はそんな今日の文化状況に対する警鐘としてこの作品を世に出したのではないかという意見も出された。(渡部 康夫)
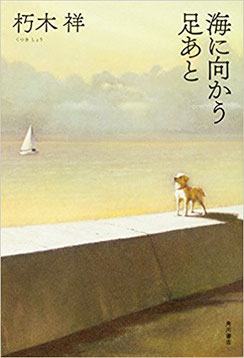
6月銀読書会 朽木祥『海に向かう足あと』
6月26日(月)午後於:千代田区立図書館
テキスト:『海に向かう足あと』(朽木祥著 ‘17年2月 角川書店)
作者は被爆2世で、広島市出身の児童文学作家。「突然、大切な人が帰ってこなかった経験を周囲の多くの人が抱えていた。これはいつか書かなければ」…そんな使命感から本作品(初の一般向け小説)が生まれた。大切にしていることは、悲しみや辛さに共感し、ともに苦しむ気持ちを呼び起こす“共感共苦”だという。
ストーリー 初めは、優雅に見えるヨットクルーの探検話かと…。村雲(30代半ばの照明デザイナー)をキャプテンに、彼と大学ヨット部同期の友人2人(政府関係機関、市役所勤務)、若者2人(ベンチャー企業勤務、ヨットニート)に定年退職者(ヨット歴40年のベテラン)3世代計6人の仲間。6人は、苦心して新しくヨット(ハープ号)を手に入れた。週末に三浦半島風色湾に集まって、翌年ゴールデンウィークに開かれる三日月島~江の島900kmのレース出場に備えて練習に励む。物語は、その年の秋から翌年レース当日までの6人の家族・恋人・動物との絆や思いを織り交ぜながら進行していく。爽快なヨットセーリング――空は青く、白く光る雲と波。やがて6人は悲しい沈黙に支配され黄昏を迎える。そして、空は黒く真っ赤に燃える海へと激変していく…。
読書会で話題になったこと この物語には、詩(詩集)や政治家のメッセージ、映画(映画人)や文学(作家や物語の主人公)、絵本、料理などが散りばめられている。それらが本作品とどう関わっているの だろうか?…そんなことを考えながら読むのも面白いかもしれない。
ホテルの書斎に掲げられた額に収められた詩、詩の帯の惹句、最後に開いた頁の詩句が作品のタイトルにつながり、作者のメッセージ、作品のテーマと重なっているのではないだろうか。
しかし、「もう一度読み直してみるという気持ちにはならない」といった感想が続出。私たち以外の人(殊に若い人たち)が読んで、「…こんな“恐ろしい幸せの中でも、不穏な風を感じる”からこそ、現政権が進めていることは正義のためのより良い選択だ!」と唱えないだろうか?…という危惧も覚えるといった作品感想が出された。(記録:田所恭介)

5月読書会『キャスターという仕事』第57回銀読書会 5月23日(火)テキスト=国谷裕子『キャスターという仕事」(岩波新書)
今月の課題図書は、『キャスターという仕事』(国谷裕子著)でした。「クローズアップ現代」のキャスターとして23年、制作スタッフとともに報道の新しいスタイルを作り上げてきた国谷さんが、番組とともに過ごしてきた時間を整理し自分なりの区切りを付けたいと考えて著した本であり、国谷さんの挑戦の日々を語った記録です。テレビの報道番組が抱える難しさと危うさの中で、番組を制作する人たちの思いを背負って、様々な問題を世に問い続けてきた国谷さんは常に「言葉の力を信じ」「今という時代を映す鏡でありたいと願った」そうです。読書会はいつも通り「あらすじ」「テーマ」「作者」についての説明や考えを、それぞれの担当者が発表し、「印象的な場面・フレーズ」「今日の状況・身近な経験」と続きます。印象的な場面や今日の状況については、担当者だけでなく参加者全員思うこと・言いたいことがいっぱいあって、発言が尽きません。参加者は8名と、いつもより少なかったけれど、あっという間に時間が過ぎてしまいました。この日の夜、共謀罪が衆議院を通過したのも複雑な思いの読書会でした。(記録:廣畑環)

4月読書会=『みかづき』(森絵都著・集英社)4月27日(木)
この作品は、戦後の学習塾の歴史を縦糸に家族のつながりを横糸に紡いだ小説である。
もはや戦後ではないといわれ、世の中が落ち着いた頃、学習塾の黎明期を迎える。その後、教育政策の変遷に伴って、熾烈な塾の生き残りをかけた生存競争の時代となる。そして、塾が社会的に認知されるのだが、格差社会が進むことにより貧困のため塾に行けない子どもたちのために学習支援を模索する時代を迎える。そんな歴史の中で真剣に学習塾経営に向き合った家族三代の50年間にわたる営みを描いている。
第1章から4章までは、塾創設者の一人大島吾郎中心に描かれているが、第5章は、妻の千明、第6章からは子どもの蕗子、最後の8章では孫の一朗が中心に描かれている。それらすべてが主人公ともいえるが、多様な人物を描くことによって戦後という時代の多様性を描こうとする作者の意図が見えるのではないか、そう考えると、登場人物が関わり続ける学習塾そのものが主人公と言えるのではないかという意見も出された。印象的な場面は、吾郎が56冊目の本の出版記念パーティで述べたスピーチの言葉と言う意見が出された。「最近の教育はなってない、これでは子どもがまともに育たないと誰もが憂い嘆いている。・・・・常に何か欠けている三日月。教育も自分も同様、そのようなものであるかもしれない。欠けている自覚があればこそ、人は満ちよう、満ちようと研鑽を積むのかもしれない、」(本書464ページ)という言葉によって、この本の題名を「みかづき」にした作者の思いが明かされるのである。
今日の教育現場は、格差社会が進行している。貧困のために進学塾に通えない子どもが希望する学校に進学できない状況がある。この作品によって戦後の教育をふり返り、これからの教育のあり方を考えるヒントを得ることができるのではないだろうか。(渡部康夫)

3月の銀(しろかね)読書会は、昨日3月23日(木)午後、『マラス~暴力に支配される少年たち』(集英社2016.11)をテキストに行った。今回は第55回となるにあたり、著者の工藤律子さん(フリージャーナリスト)をお迎えして行うこととなった。
これは「世界で一番危ない」と言われるホンジュラスにおける暴力組織「マラス」の実態に迫ろうとして、そこの取り込まれていた若者や、そこから抜け出てその支配下にある若者を救おうとして努力している人たちを取材したドキュメントである。331ページという分厚な本だが、読み始めると、少年たちの「その後」を追って一気に読んでしまう。
貧困の中で「未来」とか「希望」とかいう言葉すら思い浮かべることがない境遇に置かれた少年たちが、身近な存在としてタトゥーをして地域を闊歩する「マラス」の若者にあこがれるようになるとことはよくわかる。そしてひとたびそのメンバーとして踏み込めば、「死への恐怖」に支配され、5年先、10年先には「消えている」。

その中から抜け出して、教会をよりどころに神の道、正義への道に踏み出すよう働きかける人々がいることに、深い感動を思える。「人は本来信頼できるものである」との思いを強くする。マラスが組織を抜け出すものを許さないが、「神の道」に進もうとするものだけは許すということにも、感銘する。「信仰心薄い日本人」である私には信じられないような事実だ。
最近の日本の教育を見ると、子どもは(人は)しつけなければ悪に進む、早いうちに善なる知識と道徳を埋め込まなければいけないというような、人間不信に立った強い使命感に燃える教師たちが子どもたちの前に立っているように見える。それは「教育者」ではなく、「調教師」のようだ。教室には笑い声もない。楽しみも安心感もない。塾以上の緊張感が支配している。
工藤さんは取材の過程で出会った若者たちの素顔をパソコンで見せてくれた。立ち直っていく彼らはとても明るい。彼らを支える人たちがいるのだ。この世界への希望を失いつつある人にはぜひ読んでほしい。この目の前の華奢な女性がマラス支配地域に取材してここにいるのだと、あらためて感銘を深くした。
今回は参加者が15名となり、いつもの会場は手狭なため、近くの「香りの図書館」会議室をお借りした。次回は4月27日13:30~。千代田区中央図書館9階研修室です。テキストは森絵都『みかづき』(集英社)。誰でも参加はできますが、会場の都合上、参加ご希望の方は事前にお知らせください。(記録:岩辺)
